文章を書くことを生業にしている人たちの話です。
それぞれ思い思いに書くことについて述べており、15人もいるのでそれぞれがとても個性的です。
たとえば芸人さんの記述はかなり砕けていて、内容もとてつもなくぶっ飛んでいます(笑)
反対に物理学者の方もいて、その方の文章は硬いというか使われる用語も少しむずかしいものが多くて読むのに集中力が必要でした。
そんな個性豊かな面々のお話の中で、特に興味を惹かれた3人を挙げたいと思います。
好きからはじめてみよう
まず一人目は石山蓮華さんのお話。この方のお話は全編、電線のお話です。
肩書きは電線愛好家で、電線の魅力について語っています。
幼少期から電線に惹かれて、ちゃんと好きだと言えるようになったのは大人になってから。
その情熱は、写真にしてまとめたり、同人誌30冊と少量ながらも完売したりと好きなことを追求する姿勢になんだか心躍りました。
どうして電線が好きなのか、石山さん自身でもうまく説明できなかったそうです。まあ好きなものってそうですよね。好きだから好きなんだもん、みたいな。
人からなんで電線が好きなの?と数多く聞かれることへの答えを出す必要から、なぜ好きなのかを自身へ繰り返し問いかけ、言語化してきた経緯から言葉にすることの大切さを説いています。
それにしても電線が好きとは。人の個性って無限というか意外なことが好きな人がいるんだなぁとすらすらと読めました。
書くのは大変なこと?
二人目は、武田砂鉄さんというライターの方です。
ライターの仕事をパン屋にたとえて書かれていました。
傍目から見て大変なのはパン屋もライターも同じ。でもやってる本人からしてみたら当たり前なことをこなしているだけで周りが言うほどしんどく感じない胸の内を吐露していました。
ほかにも
・パン屋でいう売れる看板商品(自分の強みの文章)を作ること
・売れたらそのパンが店の顔になるのでそのままだと自分を狭めてしまう。隙を見て他の系統のパン(違う分野の文章)も試してもらうこと
・常にお客さんの需要と自分の思いとの板挟みがある
などリズムの良いたとえ話が読みやすかったです。
安易なフレーズを用いない
三人目は、文学紹介者の頭木弘樹さん。
この方は体験記についての言葉選びについて注意を促しています。
文章を書く際に型を使うことは大変有用とされています。
いろんな人が勧めていますし、たくさんの人がさまざまな型を参考に文章を書いています。
誰もが簡単に使える反面、内容によっては使い古された感のある表現になってしまい、読者(受け手)を辟易とさせてしまうことも。
あるライターさんの話。
「おすすめ〇〇3選、〇〇を勧める5つの理由、のような記事の最後のまとめに入ると決まって、『いかがだったでしょうか』というフレーズが入ります。ちょっとイラっとしますね」
繰り返し同じパターンを見せられると人は不快に思うのかもしれません。
頭木さんの場合、世界中の秘境を旅した人と接見する機会があり、さぞかし普通とは違う話が聞けると思ったら、「人との出会いが大切」「あきらめないことが大切」「考えるより行動すること」とか、おそろしく平凡なことしか言わなくてガッカリしたとか。
話し手が貴重な体験を持っていても、伝える言葉が使い古されたフレーズのみだと凡庸な印象を与えてしまいます。
それでも、たとえ言葉が豊富でなくても、希少な体験のエピソードや熱意を持って話せばまた違っていたかもしれませんが、その伝える努力を怠ってしまったようです。
ほかにも惹かれる話が多数
15人それぞれ違った経歴であり、それぞれが人生で体得してきた文章論はその人でしか出せない味というか、説得力があります。たとえば
・読み手が考えたり余韻に浸ることをうながすためにあえて書かないこともあり。
・書けないときはムリに書かなくていい。今書く時期じゃないというだけ。毎年本を出していたが書く気がなくなり1年休んだら自然とまた文章を紡ぎたくなり再開した。
・文章を書くのが向いてない人に短歌や俳句を勧めたらそちらの方面で才能が開花された話。
など、興味深いエピソードが散見しています。
読んだ人にとっての特別がある
個性豊かな15人の文章。読んだ人はその中の誰かに、どこかしらの文章に、ハッと気づかされる。そんな良書でした。
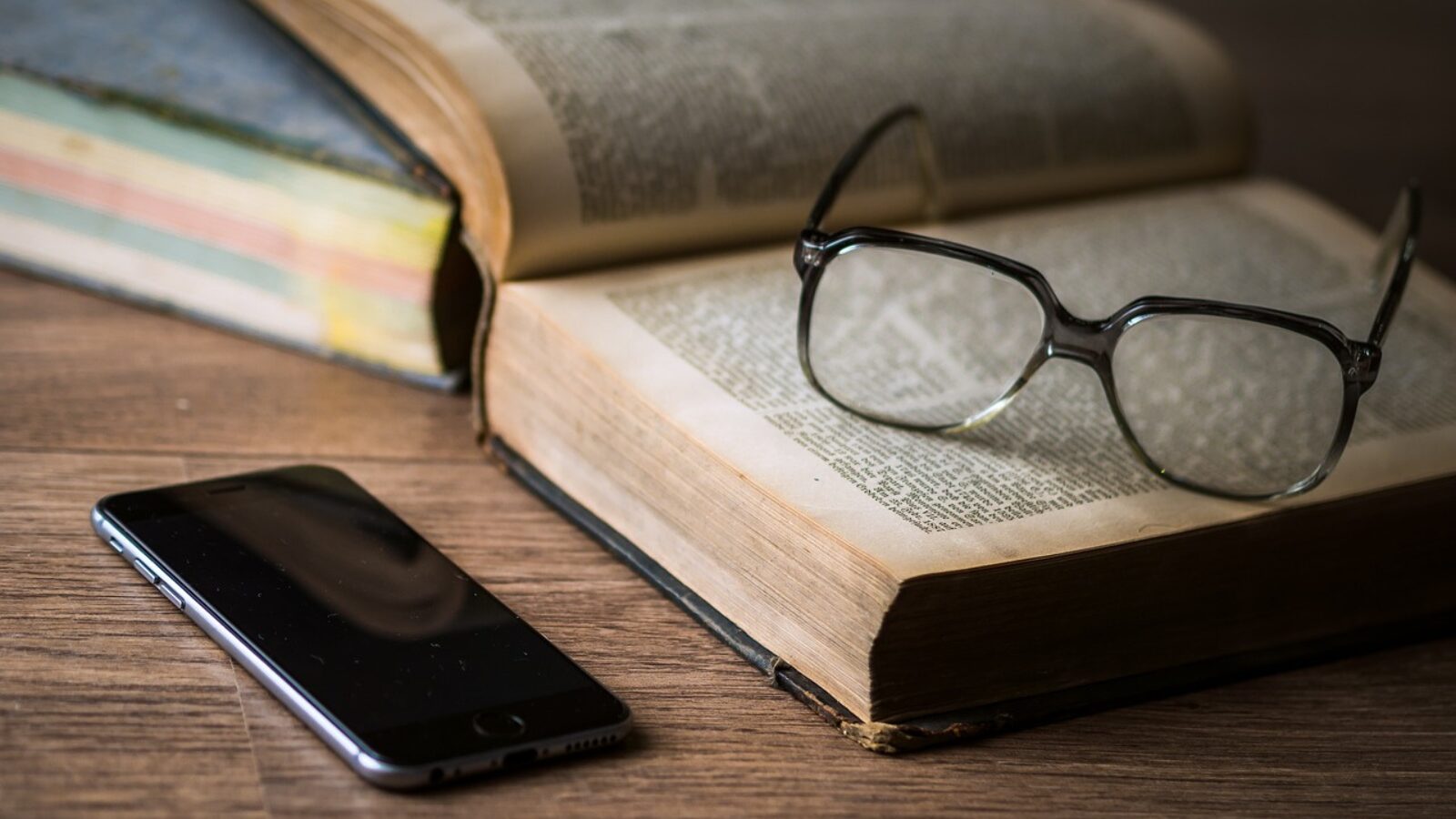


コメント