今回マスターアーカイブの本の内容を要約したものを掲載しています。
実際の本は、かなりの容量になっておりますので、気になって一度全部目を通したい方は購入をおすすめします。
かなりの文章量なので読み応えは抜群。その分冗長な部分もあり、知りたいけど読むのが大変という方向けに、自分にとって興味深いところを中心に抜粋して要約してみました。
νガンダムの試作機が開発される
ZZガンダム物語終了時、戦後復興と経済の立て直しのため、軍費を収縮。MS配備の予算も減らされる。
これまでの開発投資の回収を目論んでたアナハイムは困った。国防を理由にジェガンの配備だけは死守。しかし儲けを上げるにはZガンダムなどのハイエンド機を売り込みたい。
そうした中で、軍上層部に「ガンダムの再来」を望む話が出る。理由はネオジオンに首都を占拠された屈辱感がそうさせたのか、と推察されるが真偽は不明。
どちらにせよ、アナハイムはチャンスとばかりに目をつけ、のちに世に出るνガンダムにつながる試作機を開発することになる。
コンセプトは大型非可変試作MS
当時主流であった19メートル級の機体より大きい20メール超級の大型機体フレームに高出力ジェネレーターを搭載、さらにサイコミュ兵器を含む様々な武装オプションを搭載することも視野に入れる。
ガンダムの再来を望む軍上層部は初代ガンダムと同じ非可変MSを所望した。
それに対しアナハイムはこれまでの可変MSに莫大な開発費を投入、研究してきたノウハウを活かすことを望んでいた。
しかし結果として軍上層部の意向に異を唱えることはできなかった。
可変MSのハイエンド機は開発、整備などあらゆる分野のコストが跳ね上がる傾向にある。
いかなアナハイムでも、軍縮時代である今のハイエンド機のあり方は非可変MSであることを認めざるを得なかった。
RX-9x系試作機がベース
ブライトの図らいによって、地球連邦軍がアナハイムに開発させていた新型機をロンドベルにまわす段取りをつける。
この開発させていた新型機が、前項のRX-9x系試作機である。これを元にアムロの考えが反映されて仕様変更が行われたのち、完成したのがRX-93 νガンダムである。
つまりνガンダムはアムロがゼロから設計したわけではなく、機体の大枠はすでに存在していた。
アムロが進言したのは、サイコミュの導入、外装形状の一部変更、メンテナンス性と拡張性を確保するためのユニットの構造化である。
RX-9x系試作機をベースにそれらを加え、ファンネルを含むサイコミュ兵装を持つ第四世代MSとして完成させることとなった。
サイコミュの適用
νガンダムの大きな特徴としてサイコミュシステムが挙げられる。
機体制御の補助を目的としてZ系由来のバイオセンサーを搭載し、リニアシートのヘッド部分に感応波受信パックが備え付けられている。
これに加えて、攻撃端末としてフィンファンネルの運用を想定し、その遠隔操作に必要なデバイスを搭載。
アナハイムが準サイコミュとして開発したインコムデバイスの技術も取り入れられる等、同社が保有しているサイコミュ関連の技術を惜しみなく投入されている。
これらの機能が、機体の完成間近に追加されたサイコフレームによって効果が底上げされ、当初の見通しを大きく超えるサイコミュ性能を有する機体へと仕上がることとなった。
採算は度外視
このような特徴を持つRX-93はワンオフモデルであり、かつハイエンド機を実現するため採算は度外視している。
生産期間の短縮のため規格品も多用しているがその反面、次世代機への採用を視野に開発されていた部材も積極的に採用している。
その部材は従来品よりはるかに高価であったが惜しみなく取り入れた結果、機体の強度と軽量化に大きく貢献した。
量産化への試みもあるが限定的
量産化も視野に入れたためか消耗率の高い駆動系や推進系のデバイスには規格品を採用し、消耗品でないケーブルや機体フレームには高品質の素材や新規設計の部材を用いている。
ほかにも胸部ダクト内に存在する探知機器のユニットや推力関係機材など可能な限り量産機の規格を採用している。
しかしパイロットがアムロであることを前提としているため、制御系はサイコミュ・チップが用いられ、基本制御系はすべてサイコミュ対応機器に取り替える必要があった。
結果的に他MSとの部品共用は限定的なものとなっている。
ワンオフモデルや次世代機仕様の数々
コクピット
コクピット周辺にサイコフレームを導入されているが強度は従来の構造材より劣る。
容積制限の都合上、単純に全体の厚みを増して強度を取り戻すといった処置ができない。
したがって折り曲げや肉抜きなど手間のかかる加工を施した部材を組み合わせて作り直す必要があり、ほぼワンオフと言っていい構造となった。
さらに後述するスラスターの改良による高Gの対処として、コクピット支えの機構も新たに開発している。
バーニアスラスター
一年戦争時以降マグネットコーティングの適用によりMSの四肢の動きをニュータイプの反応速度に対応することができた。
しかしバーニアスラスターの反応においては一年戦争時MSと現行MSとの優劣はほとんどない。
RX-93ではバーニアスラスターのレスポンス向上の実現を目指し、開発されている。
すなわちスラスターが最大出力になるまでのタイムラグをできるだけ減らすことを目的とした。
試行錯誤の結果、急速加熱の新システムを開発し、さらに使われるプロペラント・ペレット(推進薬)にも改良を加えた。
この二つの改善により、バーニアスラスターのレスポンスは大幅に上昇し、脚部まわりだけでもジェガンタイプMSのメインスラスターに匹敵する推力を得ている。
だが反応速度が早まったが故に問題も発生した。機体の急激な加速にパイロットの体がついていかないという問題だ。
これを解消するために、コックピットを支える機構を新たに見直し、機体の運動とは反対方向に球体コクピットを回転させるなど、急激なGを緩和する処置が取れるよう改良を施した。
武装
ビームサーベル
AE社が次世代デバイスとして試験中のハイエネルギータイプの試作品。
ビームライフル
次世代MS用火器として試作されていたメカニズムを使用している。
ハイパーバズーカ
特殊な次世代デバイスの仕様はなかったが、サイコミュ・チップを発射指示コンピューターに内蔵、感応波により遠隔操作が可能である。
これによりバックパック中央にマウントした状態で発射するという荒技も可能であった。
これは前述したパイロットをアムロに据え、基本制御系をすべてサイコミュ対応機器に取り替えたことによる、機体本体の高性能化による恩恵といえる。
感想
νガンダムのマスターアーカイブが発行されたのは2019年で、それまでのνガンダムのイメージはジェガンと共有パーツの多い、信頼性、整備性に特化したものであり、高性能なMSの印象はありませんでした。
しかし今回のマスターアーカイブでは、量産を視野に入れつつ、大枠は採算度外視でハイエンド機(高性能)を目指したという記述があります。
言葉の通り、随所にワンオフモデルや次世代モデルの技術が惜しみなく投入しているところがあり、それまでの平凡なνガンダムのイメージとは異なり、大変興味深かったです。
特に、バーニアスラスターのレスポンス向上は読んでておもしろかった。
ほかにもたくさんの説明、解説が記載されています。
今回νガンダムと直接関係ないので割愛したのですが、アナハイムがリックディアス建造の際独自に作り上げたムーバブルフレームなど、多少難解ですが非常に読み応えがあり興味がそそられる内容でした。
全体的にも結構ボリュームがあるので、腰を据えて読みたい人などにおすすめです。
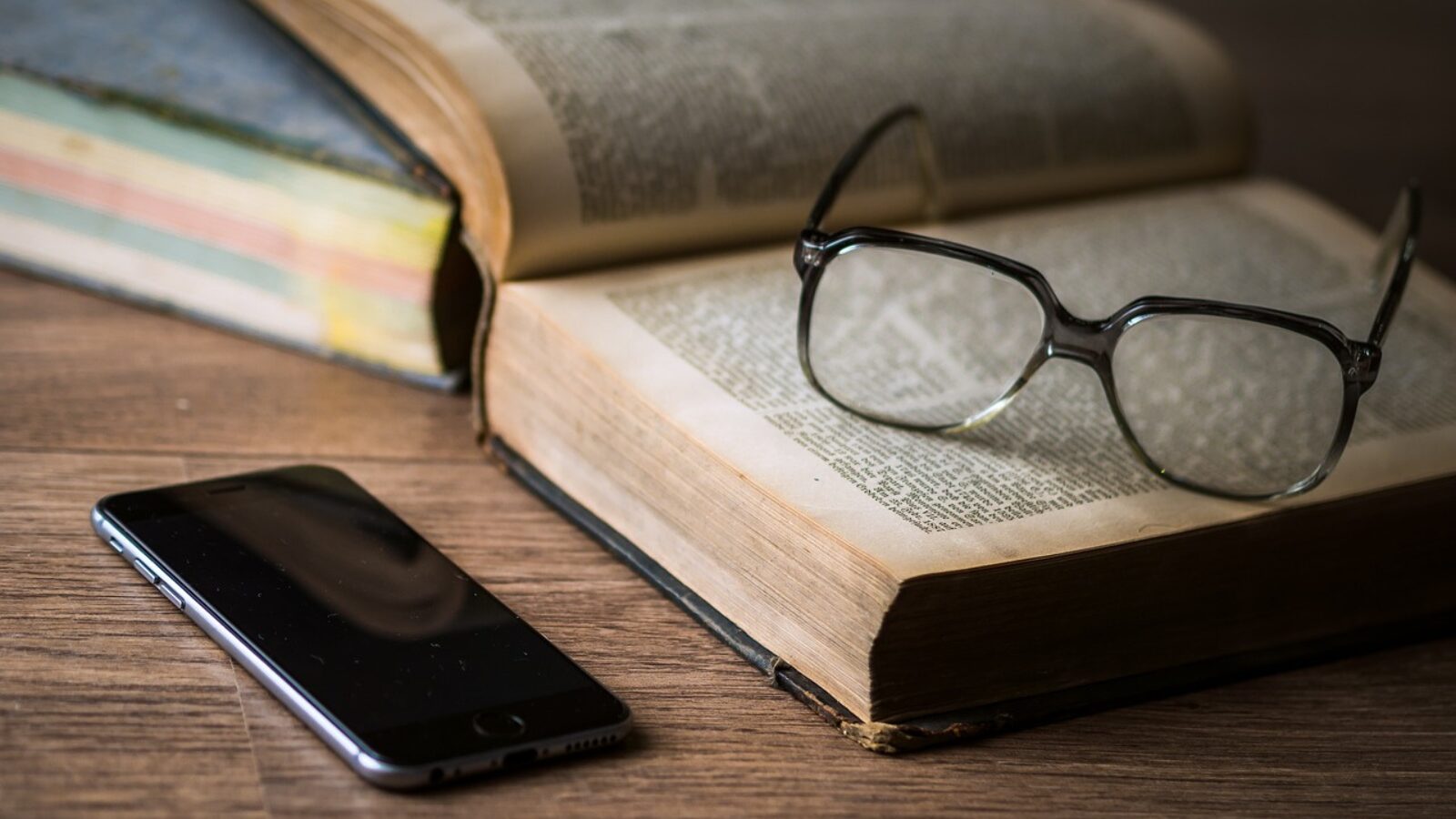


コメント